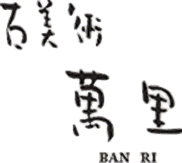藍九谷花文碗形向付猪口大振系
江戸前期、寛文期、1660-1670年代前後
①D10.9㎝(11.2) H6.0㎝(6.1) W135g 完品 ¥25,000-
他に完品3客、他に高台のみ小ホツ有1客
詳細はお問い合わせください
:
新しい年に使う古九谷のご飯茶碗?
ありました〜😀
:
江戸前期の染付古九谷、藍九谷、
生まれは大振系向付なんだけど…
ご飯茶碗にぴったり!です🤗
:
江戸前期、
古九谷のお客様は、お茶を嗜む富裕層が中心でした。
お茶席の大振系向付、
この形、このサイズ、ふっくら形、あったんですね🤭
(伊万里のご飯茶碗の登場は100年程後、1760年代以降)
:
おおらかな文様が流れる様、側面全体に、
花の様な、蕾の様な…
高台二重圏線、
内側見込に花一輪、見込と縁に二重圏線、
藍九谷のしっとり釉がたっぷり、
ふっくら優しい器形です。
薄作りで軽くて口当たり最高!です。
:
ご飯茶碗の登場は?
1760年代、将軍が初めて磁器の御飯茶碗を使ったという記録があります。
(磁器は高級品で庶民は木の器•漆器、素焼きの土物等を使用)
江戸幕末期にはかなり普及しています。
文化文政期の頃から少しずつ広まったと考えられます。
:
軽〜く一膳の御飯かな?と思います。
水だと口縁1㎝手前、180ccが余裕で入ります
:
Condition*
:
①微妙に楕円気味、気にならない程度
少し紫を帯びた呉須色、綺麗な発色
:
②D10.9㎝(11.0) H6.1㎝ W125g ¥25,000-
内側小さな凹部に制作時の染付文様⁈気になっってカバ-⁈
(釉薬がかかりしっかり補修、ダメージ無、画像参照)
高台付け部に釉切多数
ほぼ真円、気にならない程度
紫を帯びた呉須色、綺麗な発色
:
③D11.0㎝(10.8) H6.0㎝ W135g ¥25,000-
高台上、花下白磁部釉切多少集中
ほぼ真円、気にならない程度
少し紫を帯びた呉須色、綺麗な発色
:
④D11.7㎝(10.9) H5.9㎝(6.1) W125g ¥20,000-
かなり楕円、気にならない方にお勧め
ふんわりな仕上がり、滲みではなく暈し的な印象
:
⑤D11.1㎝(10.8) H5.8㎝(6.0) W125g ¥20,000-
高台畳付から側面にW4x2㎜のホツ、座りに支障無
見込圏線脇に5㎜程の釉切、
微妙に楕円気味、気にならない程度内かな?
少し紫を帯びた呉須色、綺麗な発色
:
共に、
極小灰振•クッツキ•釉切•シワ•釉スレ•濃淡斑•凹凸•ムシクイ多少
:
詳細画像をお送りします。お申し付け下さい。
:
FirstEdoPeriod, around 1660-1670s
D10.9㎝(11.2) H6.0㎝(6.1) W135g perfect
¥25,000-each
Other perfect, 3P, small chip on the foot, 1P
Please ask details


A 藍九谷 花蕾 碗形向付猪口
¥25,000