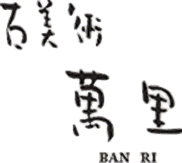古九谷鸚鵡切り株八角紅縁五寸皿 SOLD
江戸前期 1640〜1650年代前後
D13.4㎝(14.2) H2.8㎝(2.4)共に最大 小紅押さえ有
詳細はお問い合わせ下さい。
:
鸚鵡(オウム)? インコ? カラフルな鳥?
オウム、だったらいいなぁ‼️
:
ShibataCollection Part3 No114 掲載作品とほぼ同手
(図録には岩鳥文、と紹介)
(描かれた鳥の正確な名称は難しい、鳥は正解😄)
:
オウムやインコはいつ日本に?
奈良時代、平安時代から、と言われています。
(文献に鸚鵡という文字があるみたいです)
インコもオウムの仲間なんです!
(通りで!インコもお話上手!なんですね!)
:
江戸前期の古九谷、厚みのある手、
立派な切り株に大きな鳥を黒縁取りで、
赤•緑•青•黄色を加彩、
立ち上がりに染付櫛文、
八角紅縁仕上げ、
裏四方に染付花葉散らし、赤を添えて、
高台二重圏線、二重角福銘、
ちょっと深さのある五寸皿です。
:
日本初の色絵磁器、古九谷は、当初、
中国の南京赤絵をお手本に作られました。
(古染付同様、明末清初に作られた色絵磁器)
ちょっと厚手のしっかりした平向付皿です。
:
日本初の色絵磁器、古九谷は大人気だった様です。
何故⁉️
当時、日本人にとって憧れの中国色絵磁器、
一握りの富裕層、日本の茶人たちが好み、多く輸入されていました。
待望の国内産、色絵磁器製産、待ってました‼️
だった様です。
:
大きな需要は、古九谷の大きな技術発展に繋がりました。
:
初期伊万里のすぐ後、日本初の色絵磁器生産、
窯中の温度調整はまだまだ未熟でした。
色絵は、染付文様乾燥後、釉掛け窯出しの後、
釉薬上に文様を描きます。
(染付は1300度程、色絵は800度程)
:
染付で縁周りの櫛文様を描く、
乾燥後、釉薬を掛け、窯の中に、
窯から出して見ると…
ちょっと温度の低い所で焼成した⁈
釉薬が少し厚めで小さな釉切が多い、
でも、原材料は高額、許容範囲内と判断、このまま次に、
鳥岩(オウムと切り株⁈)、全体の文様を描き、
再度、低温度の窯に、
今度はちょっと温度が高すぎた⁈
緑•黄色が少し煮え気味、
特に黄色は薄くなってしまって…
でも、これも許容範囲内、出荷完了、ですね!
(勝手に、職人さん会話の想像、でした😆)
:
古九谷鸚鵡切り株八角紅縁五寸皿
江戸前期 1640〜1650年代前後
D13.4㎝(14.2) H2.8㎝(2.4)共に最大 小紅押さえ有 SOLD
詳細はお問い合わせ下さい。
:
Condition*
小さな紅縁押さえ巾2㎜•3㎜、画像参照
(3㎜紅押さえから、表のみ、2㎜の極薄い釉下ジカン有)
(ニューではなく、裏に通らずダメージ無)
:
キズではありませんがご確認下さい
:
色彩の濃淡•滲•スレ多少、上記説明も参照
(特に、黒縁取りはかなり薄くなっている)
紅縁に紅濃淡斑•ムシクイ•凹凸多少
極小灰振•釉切•シワ•濃淡•凹凸•釉スレ等多少
:
綺麗な八角形ではなく微かに歪み気味、左右全高差多少
(座りに支障なく気にならない程度、画像参照)
:
FirstEdoPeriod, around 1640-1650
D13.4㎝(14.2) H2.8㎝(2.4) SOLD
A tiny chip on the red edge
2 chips, 2㎜•3㎜, Repaired with lacquer.
please ask details