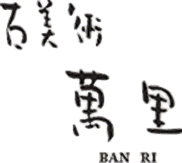古九谷
江戸前期、寛文期、1650~1670年代前後
D14.6㎝(14.4) H2.0㎝(2.4) BD7.6㎝ 完品
:
ドキッとする古九谷の独特な色彩もイイ‼︎ けど…
ちょっと優しい色彩の古九谷もイイ‼︎😄
:
“お祝い事の小道具尽くし⁈“
鼓や笛、扇と短冊、瓢箪と絵巻物や箒みたいな….
群青の唐草も決まってます‼︎
唐草の向きやバックを変えるだけで、また違う印象、
面白い五寸皿です。
:
裏を見てびっくり🫢
よくある藍九谷の裏、
裏白で、高台周りの数本の染付圏線だけ、
五彩手みたいな薄作りではなく、ちょっと厚みのある手、
裏を先に見てしまったら…
どんな文様の藍九谷だろう?と思ってしまう…
普段気にしない事を考える、
そんな古九谷、
優しい色彩の可愛い古九谷、です。
:
”九谷論争“のおさらい“
:
古九谷は半世紀程前迄、石川県の焼き物、
江戸時代の九谷焼と言われていました。
昭和20年代、
古九谷と呼ばれる焼き物が、実は佐賀県有田で作られたものではないか
という説が登場し、九谷説と有田説の論争が始まりました。
「九谷論争」です。
(明治時代から疑問に思う専門家は多くいた様です)
:
有田説は、江戸時代、海外へ輸出された伊万里の古九谷との共通性にありました。
有田説を支持する説が諸外国でも登場します。
その後、考古学的に生産地遺跡の発掘調査が双方で行われました。
素地の化学分析が行われた結果、有田説で終結しました。
終結後も古九谷の名称は残りました。
ただ、その後も調査は続いています。
疑問点がまだあり、今後の研究により更に詳細が解明されればと思います。
:
1640-1670年代の色絵伊万里が古九谷、
染付の古九谷が藍九谷です。
色絵古九谷は日本初の色絵磁器、つまり…
1670年代以降の色絵磁器、柿右衛門以前の色絵伊万里なんです。
:
日本初の磁器、初期伊万里誕生からほんの30年程後に、
李朝の様な厚みのある初期伊万里から、
薄作りの中国磁器みたいな色絵や染付ができたなんて…
猛スピード成長を後押しをした人たちは誰?
:
政変により国を追われた中国磁器職人たちでした。
彼らは惜しみなく技術を伝え、改良を加えました。
1640年代、伊万里の急激な進歩は、
中国技術と日本人の高い学習能力の成果、
だった様です。
:
Condition
※キズではありませんがご確認戴きたい詳細
:
上下唐草畳付がつく状態で左右に1㎜未満の隙有
(左右を押し微揺れ、薄ランチョンマット使用で解消)
(微妙に楕円気味、側面成形の不具合、口径•全高差参照)
:
表裏に窯中の薄い煙多少、画像参照
(表は口縁厚部、その口縁下の一部多少)
(裏全体は真白ではなく薄煙、側面で目立たず)
:
色スレ•色無•濃淡斑多少、許容範囲内
(特に黒縁取•朱圏線、群青•緑は色斑多少、画像参照)
極小灰振•ムシクイ•クッツキ•釉切•釉スレ•釉溜•凹凸多少


古九谷吉祥文尽唐草五寸皿
¥80,000