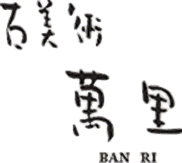藍柿右衛門元禄期花唐草襷文酢猪口ぐい呑み
江戸中期、元禄期、1680-1700年代前後
D6.0㎝(5.9) H4.1㎝ BD4.1㎝ W45g 適量50cc SOLD
小ホツ2箇所の石膏押さえ
花唐草酢猪口、ぐい呑にぴったり!
元禄享保期の藍柿猪口は….
薄くて軽くて口当たりも最高、です!
酢猪口?て、何?
江戸時代の食卓は御膳、
それぞれのお膳に酢醤油薬味等を添えて
調味料の為の小さな器でした。
20客、40客、20客倍数で出荷されていました。
(80客入の当時の木箱を見た時は本当に驚きました)
側面いっぱいに、花唐草を繊細に、伸びやかに、
薄ダミ濃淡が優しく、ふんわり仕上がっています。
上手に多い口縁の襷帯文様、高台二重圏線、渦福裏銘、
内側は透明感のある釉薬のみ、
薄くて軽くて口当たりは最高です。
毎日使ってください!
発色は、少し彩度を控えた落ち着いた色、
花唐草の上がり発色は綺麗です。
呉須発色は最初の画像が一番近いです。
日本酒好きに、お勧めです
小さな酢猪口、重量40g、口径6.0㎝、
口縁手前1㎝、50ccが余裕で入ります。
(溢れそう、なみなみで70cc弱、何事も控えめが最適?)
:
Condition
:
口縁厚から内にホツ、巾7×5㎜巾7×3㎜
(共にホツの石膏押さえ、側面は巾3×2㎜程)
(気にならなければ使用可、画像参照)
極小灰振・釉切・濃淡滲・凹凸・ムシクイ多少
共直しを取り除きました。
(キズの状態が解らない状態、共直しのカバーを取り除いた)
(修復部土台のみ残した状態、画像参照)
繊細な文様、薄濃の技、さすが藍柿です。
金粉カバー補修をするともっと良くなります。
(残念ですが完品はありません)
金継は、
桃山時代に始まったと言われています。
キズになってしまった大切な器を、使う状態に戻すお直しです。
次世代に継なぎたい日本の文化です。
(今、Kintsugiは、諸外国でも、通じる言葉になってきています)